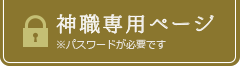由 緒
神功皇后が三韓を征して還幸の時此の地の蛇谷山に衹園天王を勧請された事に創まるという。
仁賢・天智・光仁・嵯峨・花山院・美福門院の御代にご造営或はご修理がなされ嘉応元年(1169)小松内大臣平重盛が修繕し文治元年(1185)源頼朝及佐々木六角氏頼等の造営修理があった。
この頃別当寺が建立され応神寺と称した。
応永34年(1427)2月23日田中郷領主飛鳥井中納言雅縁卿当社の詣り17日巻参籠し大般若経を転読された事が北越紀行に記されている。
又神社の後山に記念の桜樹を植えた。
世に「飛鳥井桜」「薄墨桜」という。
当時弘蔵坊・金剛院・円藏坊・王撞院・円禅坊・宝威坊・大勝院があり、これを応神寺7坊と称した。
天正年間に織田信長の兵火に罹り灰燼に帰した。
慶長3年(1598)豊臣秀吉公検地に際し、社地1町田地5段歩の寄進を受けた。
丹羽五郎左ヱ門長秀から禁制状を、又福井中納言秀康公から社領23石2斗5升の寄進を受けた。
又松平家累代から朱印状を寄せられた。
明和元年(1764)三州西尾藩主松平和泉寺乗祐が、その領邑を当国に受けた時、陣営を当所に置くと共に当社を祈願所として祭礼には必ず代参を参向させ、社殿の修築・神門の寄進・神饌料の奉納等があった。
明治元年(1869)神仏判然の令が出た時、阿麻伎美神社と称し、続いて八坂神社と改称された。
明治8年(1875)郷社に列せられ同41年(1908)神饌幣帛料供進神社に指定された。
境内末社は背後の蛇谷山嶺谷に散在鎮座されていたものを応安7年(1374)境内に移転した。
大正10年5月4日同朝日町馬場村第5号51番地字ノ西、村社若八幡神社を合併した。
昭和36年(1961)9月第2室戸台風襲来の際、当神社の境内杉木が多数倒木折損し、これを機に本殿・幣殿造営の機運が高まり、38年着工・39年竣工した。
その際、旧内陣(主神奉祀)の床檀下より多くの仏像・仏具が収納されているのを発見した。
いずれも平安末期以降のものと鑑定され、その中仏像4躯(いずれも半丈6)と光背1面が重要文化財に指定さらた。
指定を受けた諸仏像と光背は49年より逐次京都美術院で修復された。
一方これを収納する収蔵殿は昭和53年に境内に竣工し、修復を終えた仏像を収納した。指定以外のものでは、地蔵菩薩・天部形2躯・不動明王像・狛犬1対・貴徳面・蘭陵王面・採桑老面・(いづれも残欠)仁王像天衣(一部)獅子頭2頭・反花がある。
これらの収納仏像等は恐らく明治初年の神仏判然令に伴い、当局者によってひそかに主神祭檀下に安置されたと想像される。
室町幕府下知状2通・朝倉氏裁判状2通(進士文書)は宮座研究上貴重な資料であり、天王社御幸供奉之日記(八坂神社文書)は幸若舞の資料として最古の文書である。(嘉慶元年)